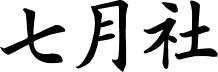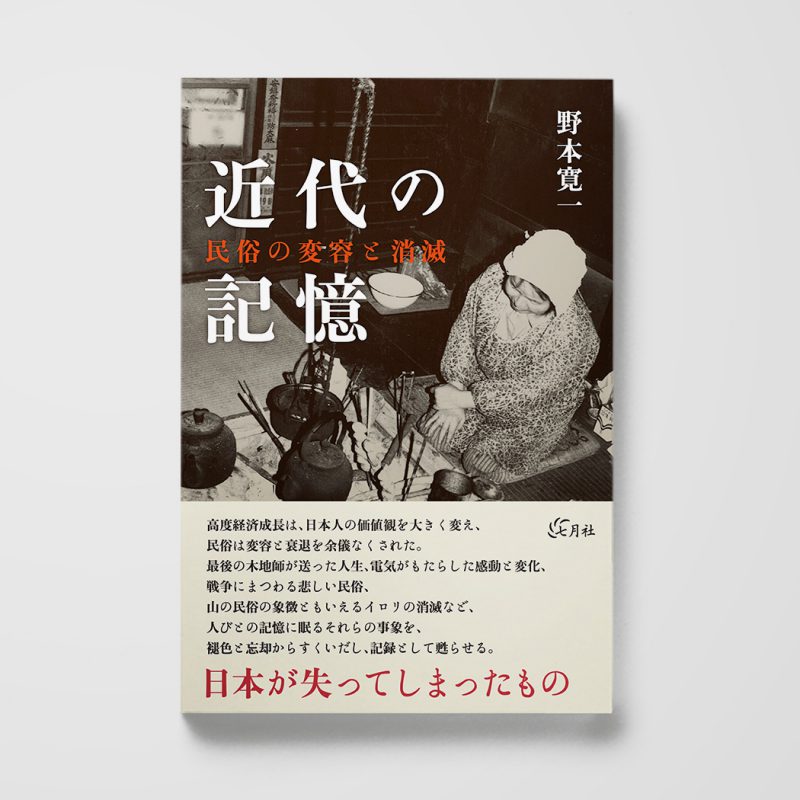兵士たちの子守唄
野本寛一(『近代の記憶』著者)
私が菅山村立国民学校(現静岡県牧之原市)に入学したのは昭和一八年(一九四三)のことだった。祖父は没し、父は戦死、伯父は南方に出征中、家をとりしきっていたのは祖母の千代(明治二六年生まれ)だった。入学祝いの膳には半分に切られた身欠鰊がのっていた。配給の品である。入学祝いは「スポーツマンナイフ」という耳なれない商標を捺されたナイフで、私がほしかった「肥後守」ではなかった。学校には奉安殿があり、校舎の外壁の板張りには木製の巨大なプロペラが固定されていた。力自慢の高等科の男子たちがこれを力まかせに手動で回転させ、回転数を競っていた。そのプロペラは大井航空隊から寄贈されたものだと言われていた。
家の北方に向けて三キロほど進めばそこは牧之原台地である。そこに横須賀鎮守府所属の飛行場が建設された。昭和一七年(一九四二)三月完成、四月には第一三連合航空隊に編入され、大井航空隊と称された。練習航空隊に指定され、偵察教育がなされていた。練習機と呼ばれる赤い機体の小型機が吹き流しをつけて毎日家の上空を飛行して南に向かった。大人たちは、相良海岸の沖にある愛鷹岩に向かって飛ぶのだと語っていた。愛鷹岩は八大竜王の島だと伝えられていた。
私の父は昭和一三年(一九三八)二月二八日、日中戦争で戦死していた。それは、私が満一歳にもならない時だった。したがって、私は父親に関する記憶を全く持っていない。学齢前後の私に対して、近隣の人びとや遠縁にあたる大人たちはよく次のように語りかけた。「お父さんの敵討ちをしなければならない」「大井航空隊に入って飛行機乗りになって仇を討つのだ」──異口同音のように聞かされた。家の後方に大井航空隊があったことも関係している。入学して一年、二年とたつうちに、自分の運動神経の鈍さを自覚するようになっていた。私は、子供ながら内心困惑した。「飛行機乗りには勉強もできて、運動神経も良くなければなれない」と聞いていたからである。子供である。平素はそんなことは忘れているのだが、大人たちから仇討ち話を聞かされると「自分には無理だろう」という思いが浮かんできて、かすかに心が疼いた。
一方、絵本の中には航空服の似合う兵士が夜空を仰ぐ凛々しい姿が描かれていた。そして傍には軍歌の歌詞が書かれていた。
恩賜の煙草いただいて 明日は死ぬぞと決めた夜は 荒野の風もなまぐさく ぐっと睨んだ敵空に 星がまたたく二つ三つ──
歌詞は記憶しているし、今でも歌唱することができるのだから、よほど心に響いていたものだと思われる。
しかし、私が軍国少年になる前、国民学校三年生の夏に戦争は終わった。家の中のラジオから流れてくる玉音放送は裏庭の柿の木の下で聞いた。もとより意味は理解できなかった。「軍国少年以前」とも言うべき年齢だったのだが、私の心の中には幼い日の葛藤が古傷のように残っている。
教科書に墨塗りもしたが、少年の私にとって釈然としなかったのは、国語の考査で旧字体を書いて数箇所罰点をもらったことだった。
高校二年生の頃だったろうか。めずらしく母が戦時中のことを口にした。──育った家の前方に滝谷という姓の農家があった。滝谷家の後継の長男善一さんが戦地から無事に帰還した。ムラびとたちが集まって賑やかに帰還・凱旋祝いをした。「滝谷善一君、凱旋万歳」──万歳三唱の声が聞こえた。母はその万歳の声を家の前の茶畑の中で聞き、しゃがみ込んで泣いたという。善一さんの帰還はムラびとと同様よろこばしいことなのだが、自分の夫はいくら待っても絶対に帰ってくることはないのだという思いがこみ上げてきて泣けたのだという。私がその母の気持を噛みしめることができたのは、『万葉集』の防人の歌を読んだ時だった。「防人に行くは誰が夫と 問ふ人を見るが羨しさ 物思ひもせず」(四四二五)という歌は心に沁みた。この「羨しさ」は深刻である。防人の歌には虚構性があるという説もあるのだが、万葉時代の悲しい「羨しさ」が近代にも存在したことは、人間として何とも情けないことだと思った。
父を戦争に奪われた私は、幼い頃から父がいないという前提で育ち、暮らしてきたので、それはごく自然のこととなり、苦痛を感じることはなかった。父のいないことに困惑を覚えたのは自分が父親になってからだった。──父親に肩車をしてもらったことも、手をつないでもらったこともない。怒鳴られたこともない。反面教師としての父親像すらないのである。父にかかわる感動が皆無である。「手探りでの父親」にしかなれなかった。とにかく父親像がないのだ。父親像が伝承されなかったのである。のみならず父親が伝えてくれるはずの伝承世界のすべてが断絶されたのである。
長男が反抗期を迎えた頃、「たまには家に居てください」という妻の言葉に対して、「俺は親父なしで育った。父親が生きているだけで上等だ」と嘯きつつ民俗を学ぶ旅を重ねてきた。ひどい父親だった。戦死の影響はその子供に及ぶばかりではなく、戦死者の孫、さらには曾孫にまで及ぶことがある。戦争の痕、そのおそろしさは、深く潜行し、尾を引くのである。
妻がある時呟いた。「満一歳にならない幼な子と別れて出征して行ったお父さんの気持ちはどんなだったでしょう」──戦地でわが子の成長を想像する。見たい。会いたい。会えない。──こうした思いを抱きながら戦地で倒れた不帰の父親は数えきれない。
平成二九年、私の母は父の命日一月二八日に一〇三歳で父のもとへ旅立った。母が保管していた父の遺品の中に私が見たことも聞いたこともなかった小さな手帳があった。それは、父が従軍中に折々のメモを記したものである。鉛筆書きの文字の中には薄くてよく読みとれない部分もあった。その手帳の中に、おそらく日中戦争中に兵士たちの間でひそかに歌われていたと思われる子守唄が記されていた。判読してみると、それは叙事性を帯びて六番まで続くものだった。
ねんねんころりよ ねんねしな 坊やの父さん国のため 遠く戦に行きました
ねんねんころりよ ねんねしな 戦闘済んで草に寝て 夢に坊やを見るでせう
ねんねんころりよ ねんねしな 坊やの父さん強いから きっと凱旋なさるでせう
ねんねんころりよ ねんねしな 父さん土産は何かしら 小さい喇叭か鉄兜
ねんねんころりよ ねんねしな もしも戦死なされたら いえいえそんな事はない
ねんねんころりよ ねんねしな 勝って帰った父さんは 大きくなったと言はれませう
夫を戦地に送り、幼子を守り育てる母の立場で作詞されたものだ。これを読んだ時、異国の戦地で、母国に残してきた幼いわが子を思う若い兵士の心が胸に迫った。八〇歳を超えた身に、全く記憶のない父の思いが深々と沁みた。
様々な子守唄に出会ってきたが、このような子守唄は全く耳にしたことがなかった。このような唄が歌われることがあってはならない。
街角でアコーディオンを弾き、ハーモニカを吹く白衣の傷痍軍人、松葉杖で電車の中に立つ白衣・戦闘帽の傷痍軍人、胸には傷痍軍人徽章が光っていた。おのおのの胸には深く複雑な思いを刻んでいたことであろう。その姿を見かけなくなってから久しい年月が流れた。
※本文章は、『近代の記憶』の「追い書き」より一部を抜粋したものです。