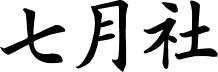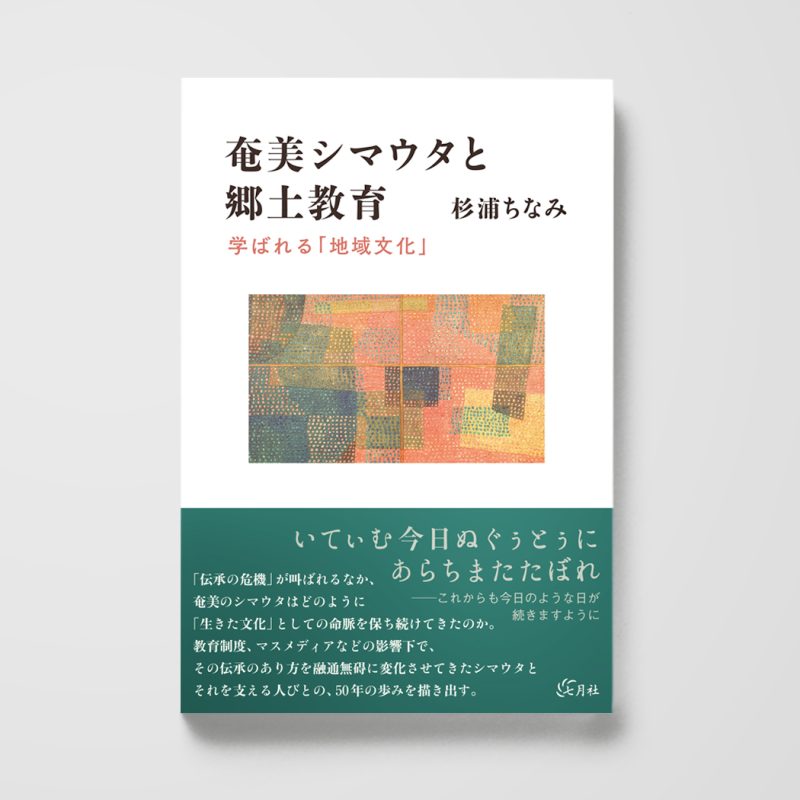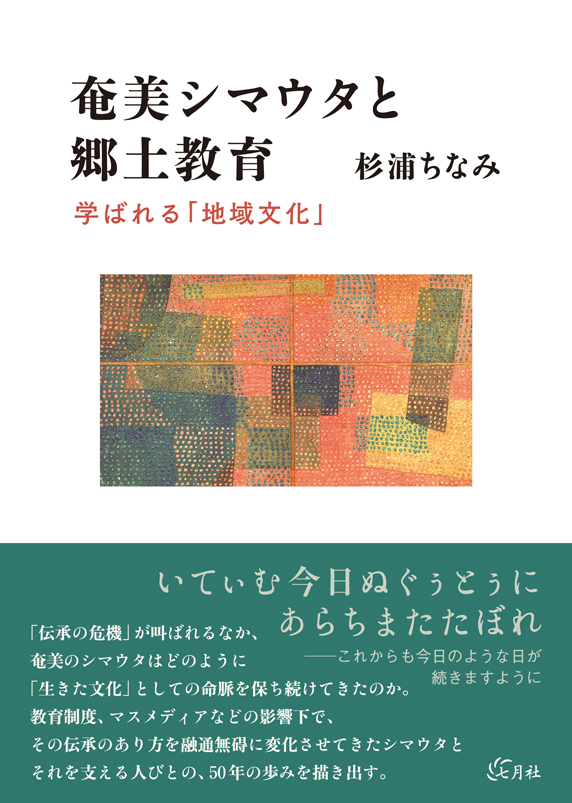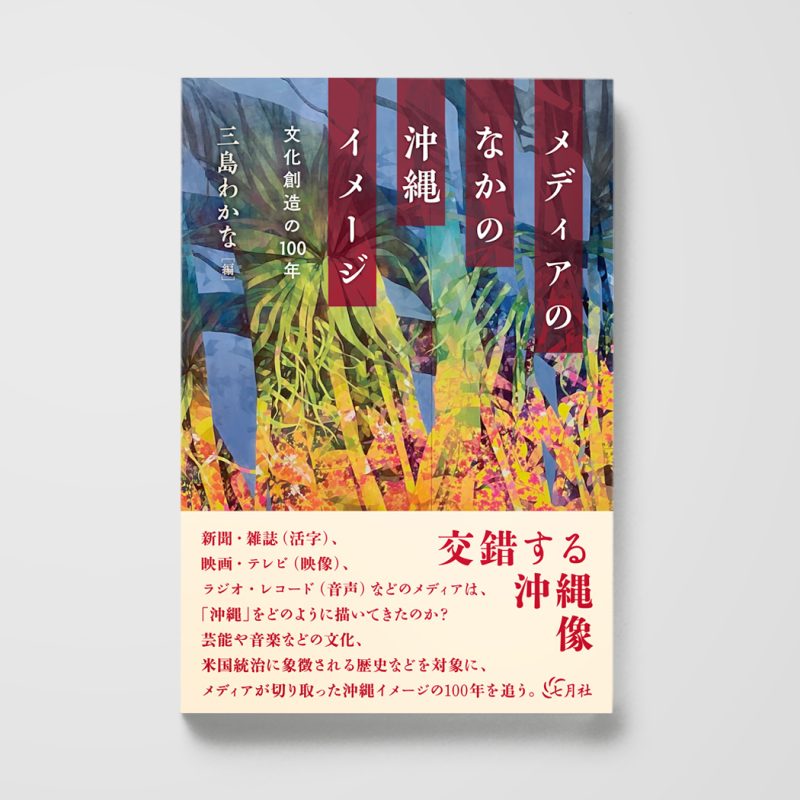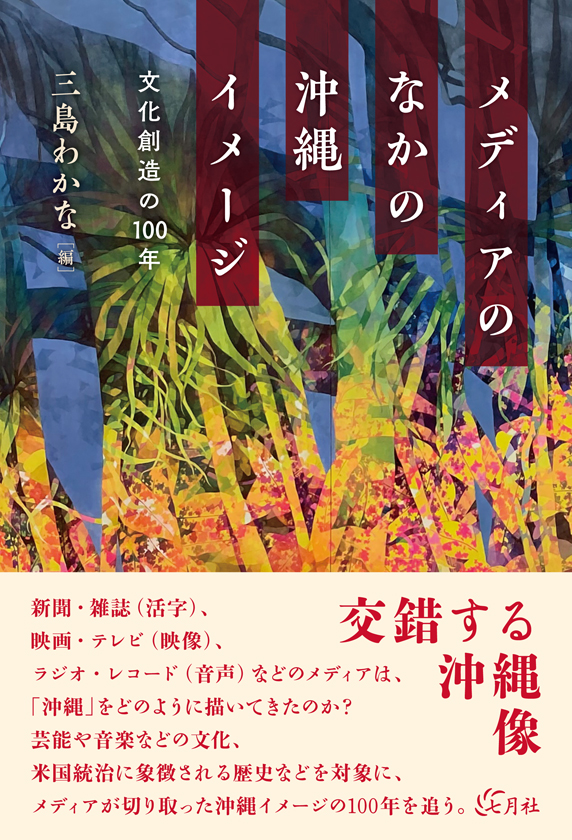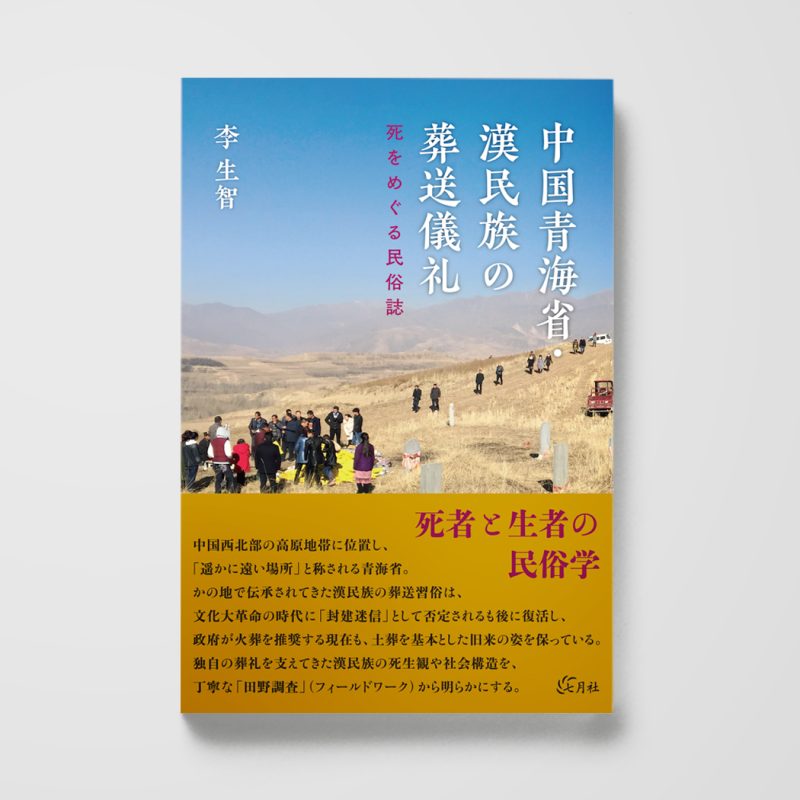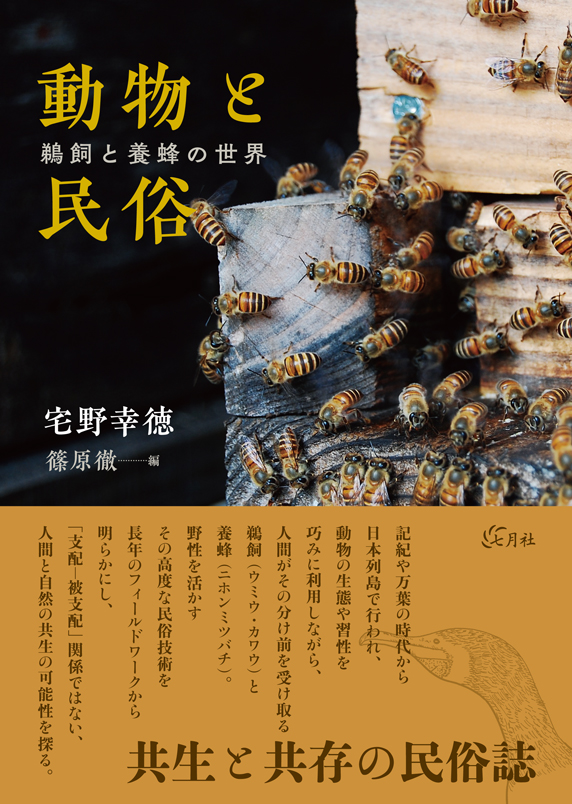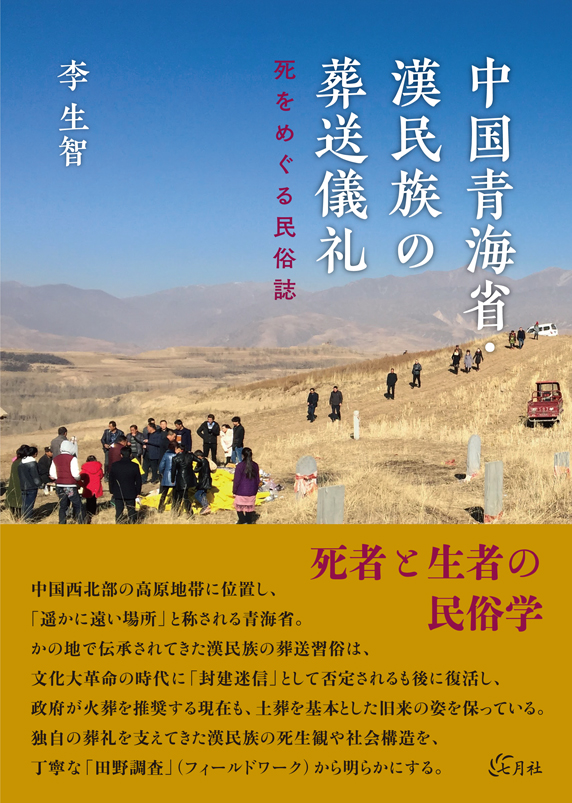変わることで伝わるもの──奄美シマウタの50年
杉浦ちなみ(『奄美シマウタと郷土教育──学ばれる「地域文化」』著者)
日本の高度経済成長期の都市文化が、きらびやかさと消費賛美と倦怠とをふりまいていたころで、子どもたちも「都会」という言葉にみんな酔い、しびれていた。東京から転校してきた女の子は絵本からぬけ出した美しさだったし、言葉がまたひどく上品だった。ラジオの長嶋茂雄の活躍に夢ときめかせ、東京オリンピックは初めてこの島にテレビを出現させた。なんだか島の生活や文化、言葉さえもが貧弱に思えた。私自身、心の中に都会への憧れが強まり、早くこの小さな島から抜け出し、大海に漕ぎ出したい思いがふくらんだ。
原井一郎「奄美の復帰後40年の来し方」(『文化ジャーナル鹿児島』No.39、1993年9・10月号、pp.12-13)
1993年、当時大島新聞社社長だった原井一郎氏はこう記した。原井氏は本土復帰直後の1954年、生まれ故郷の徳島から、母の故郷であった奄美に引っ越してきた。子どもの目にも名瀬の街の疲弊は明らかで、粗末な板葺きやトタン屋根が大半であったという。名瀬で小中学校時代を過ごした同氏は、続けて「自らの文化を卑下してきた罪深さと、地域興しさえままならぬ無能に自失、というのが大方の今のローカルの姿ではなかろうか。」と述べた(なお原井氏は現在も、奄美に関する多くの著作を精力的に執筆されている)。
この感覚は、戦後の高度成長からバブル経済の時代を地方都市で過ごした方ならばかなりの程度共有しうる感覚ではないだろうか。端的にいえば、方言や芸能といった地域固有の文化に対する卑下と、都市的なものへの憧れの感覚である。じっさいに奄美では、昭和戦後に至るまで共通語教育が学校で行われ、シマウタも生活の中で歌われこそすれ積極的に保護されることはなかった。そこには、奄美を出て「本土」で働いても不自由や差別のないように、という教育関係者の願いがあったことも無視はできない。
一方で、平成時代の地方都市で幼少期を過ごした私はこのような感覚を持たない。地域文化というものを自分の中にもたず、消費文化の中で育つ中で、地域固有の文化というものにどこか憧れのようなものすらあった(ただし、かといって国や企業が推進する地域文化振興にも違和感をおぼえていた)。それを歴史に対する無知、あるいは無邪気なオリエンタリズム、ノスタルジーとして批判することはもちろん可能だろう。しかしそれが飾らぬ実感だった。
そんななかで、大学学部生の頃に出会った奄美のシマウタは強烈な魅力を放っていた。その魅力にひかれ卒業論文、修士論文と奄美の調査を進めるうち、博士課程に進学してから、郷土教育という当初は思いもよらぬテーマを扱うことになった。対象に導かれて未知の場所に至る、というのはフィールドワークの醍醐味でもある。
本書を開くと、各地でお世話になった方々のお顔が浮かぶ。最初の調査から刊行まで15年近くかかった。お届けできないまま亡くなってしまわれた方もいる。私の不徳のいたす所というほかない。
奄美のシマウタは、生活の中で脈々と伝承されてきた、とのみ純粋に語ることはできない。本書が主に扱ったのは過去50年ほどの歴史だが、1970年代以降の民謡ブーム、文化財制度や公民館の整備、全県的な郷土教育の推進といった官民多様な要素の影響を受けつつ、少しずつ形を変えながら今日に至っている。その融通無碍さこそに奄美シマウタの魅力と本領があり、同時にそれが地域文化のもつ豊かさではないかと感じている。
とはいえ課題も多く残る。奄美の魅力を学んでいく入口に私自身がようやく立てたという感覚である。これから長い時間をかけて、探究していきたい。読者の皆様にも、本書が奄美のゆったりした魅力、その根底にあるしなやかな勁さに触れるきっかけになればさいわいである。