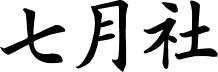〈ケア小説〉からの眺め
佐々木亜紀子(『ケアを描く──育児と介護の現代小説』』編者)
『ケアを描く──育児と介護の現代小説』は、2001年12月から始まった研究会の18年間の成果のひとつです。研究会の開催は、100回を超えました。長く続く研究会ですが、発足当初から、中心的な研究拠点はありません。連絡係も五十音順の交代です。この2点は基本的には現在も変わっていません。そのため、会合場所もさまざまです。最初は名古屋市女性会館(現「イーブルなごや」)でした。その後、名古屋、東京、奈良、神戸にある大学施設や、鶴舞中央図書館の集会室、名古屋市芸術創造センター、名古屋市生涯学習センター、京都市国際交流協会といった公共施設を利用し、宿泊施設で合宿をしたこともあります。
18年といえば、乳児が大学生になるほどの年月です。この研究会も、研究方向を見定めなかったよちよち歩きから、『〈介護小説〉の風景――高齢社会と文学』(2008年、増補版2015年、森話社)を経て、より広い〈ケア〉という視野から今回の『ケアを描く』へと歩みを進めました。
発足当初、大学院生だったメンバーも、それぞれに次のライフ・ステージに立つことになりました。就職、転職、海外赴任の経験、親やきょうだいの看取り、出産、育児など様々です。人生の新しい局面に向かうたびに右往左往しながら、それでもわたしたちが手放さなかったのは、小説を読むことと論ずることでした。
困難や多忙を抱えるほどに、小説はその行間から別の相貌をあらわし、より深く心に刻まれましたが、一人でそれを味わうにとどまらず、この研究会に集まって論じ合いました。小説の登場人物の設定や描写方法、視点や語りの方法はもちろんですが、文学研究の方法や、評価史とその政治性などもよく議題になりました。みなと忌憚なく話し、議論するのは、とにかく楽しく心躍る時間でした。
『ケアを描く』はそうした時間から生まれましたので、論者自身が心惹かれた思い入れのある小説を、各々選んで論じています。本書を通して、研究会でのわたしたちの熱く楽しい議論の一端を味わっていただければ幸いです。
研究会発足の2001年はアメリカで「9.11事件」のあった年です。それはわたしたちに、それまで見えなかった/見ようとしなかった世界の有様をつきつけました。見ようとしなければ見えないものが、世界にはたくさんあることに気づかされたのです。外側の世界だけではありません。わたしたちの足元にも、不可視化されている幾多のものがありました。
その一つは介護です。有吉佐和子が『恍惚の人』を世に出す1972年まで、日本では高齢者の〈ケア〉は、「主婦」という誰かが家庭内という見えない場所でしている〈私事〉に過ぎなかったのではないでしょうか。
育児もまた、〈公〉からは見えない領域でした。両親と女の子と男の子とが犬を連れて公園へ休日に出掛けるといった風景は、自家用車のCMにはあったでしょう。けれども、そもそも子どもを授かるまでの道程や、一人で養育を担う重圧や孤独感、育児期間に仕事上のキャリアを手放す焦燥感や挫折感は、女性個人の運命や能力として片付けられていました。レイ・アンドレは「主婦」を「忘れられた労働者」と呼びました(『主婦――忘れられた労働者』矢木公子ほか訳、勁草書房、1993年)が、介護や育児は「主婦」がする家事の一環として、長らく「忘れられ」ていたのです。
しかし〈ケア〉という切り口からは、ケアをする人/ケアを受ける人、それらの人々と共に働き、学び、生きるその多様な人生が見えてきます。〈ケア小説〉は、それらの「忘れられた」人々の行為を生き生きと描いています。
たとえば、角田光代の『八日目の蟬』では、主人公希和子が赤ん坊を誘拐する場面から始まります。そして「薫」と名づけた赤ん坊のために希和子がまずしたのは、薬局で紙おむつとミルクを買うことでした。母親がすれば当然のこととして記述されることのない行為も、誘拐犯という小説ならではの登場人物だからこそ、〈ケア〉の行為として際立ち、可視化されるのです。
わたしたちは〈ケア小説〉から、多様な生き方や新しい世界の読み方を学び、時に慰めや励ましを得、人生のステージをなんとか切り拓く支えにしてきました。本書を手に取った方もまた、〈ケア小説〉という窓から、世界を眺め、新しい小説との出会いを楽しんでくださることを願っています。