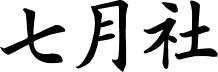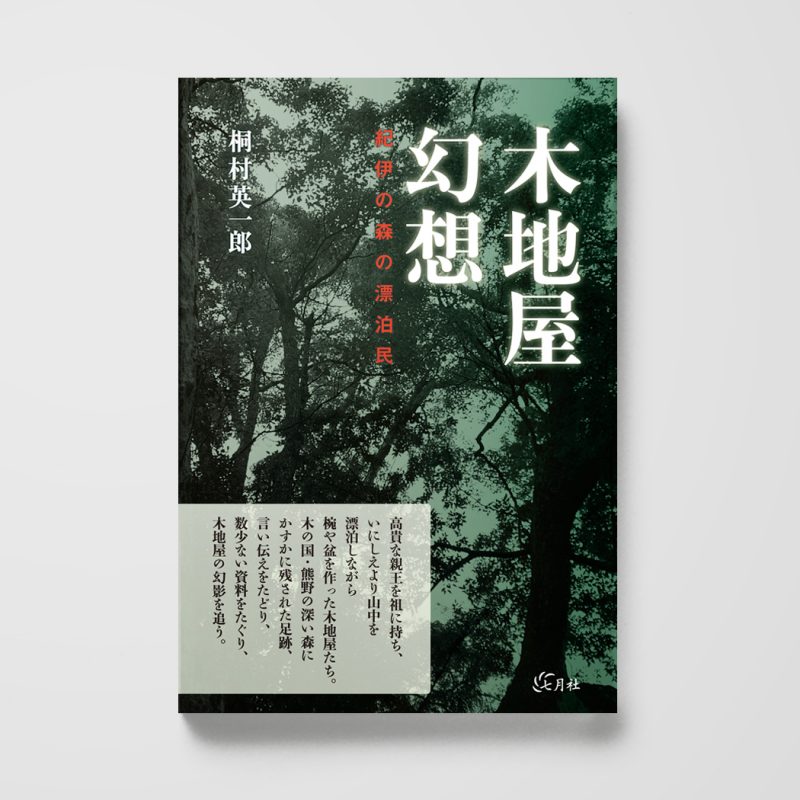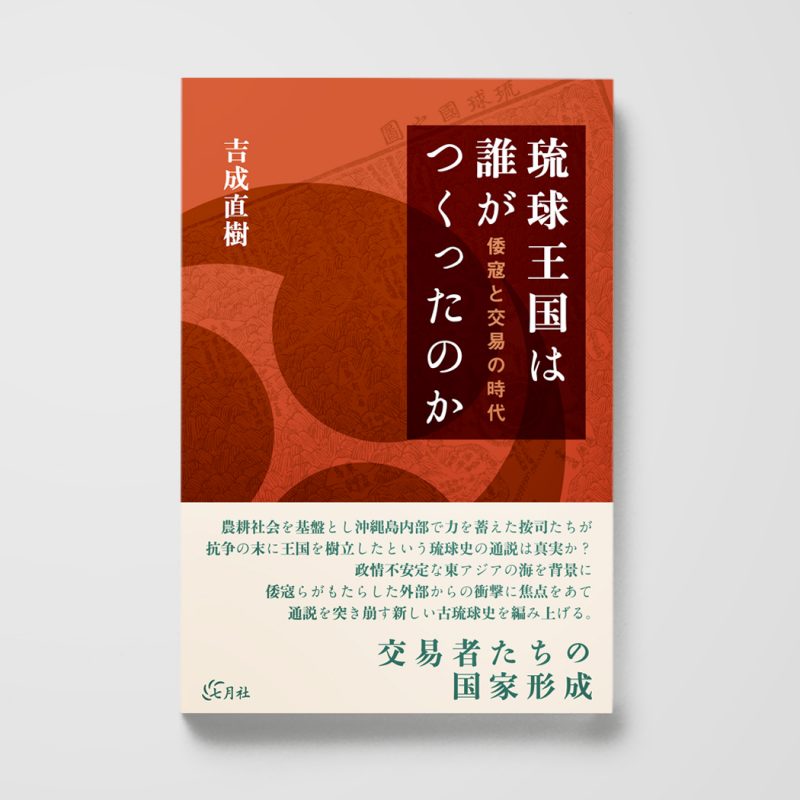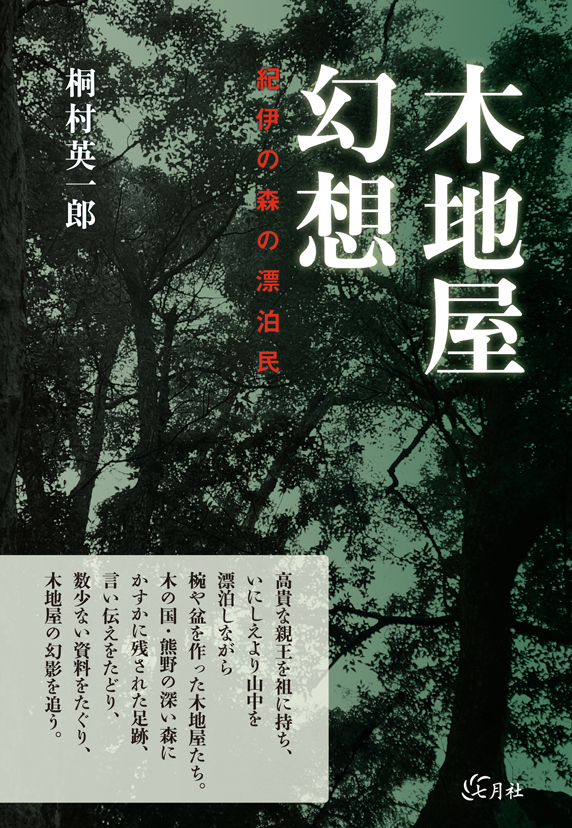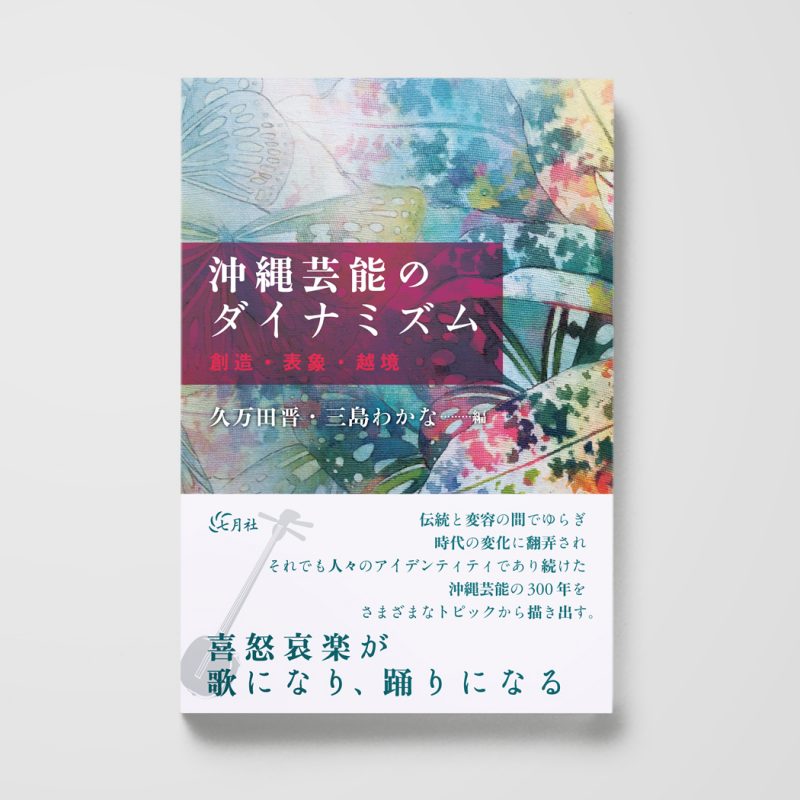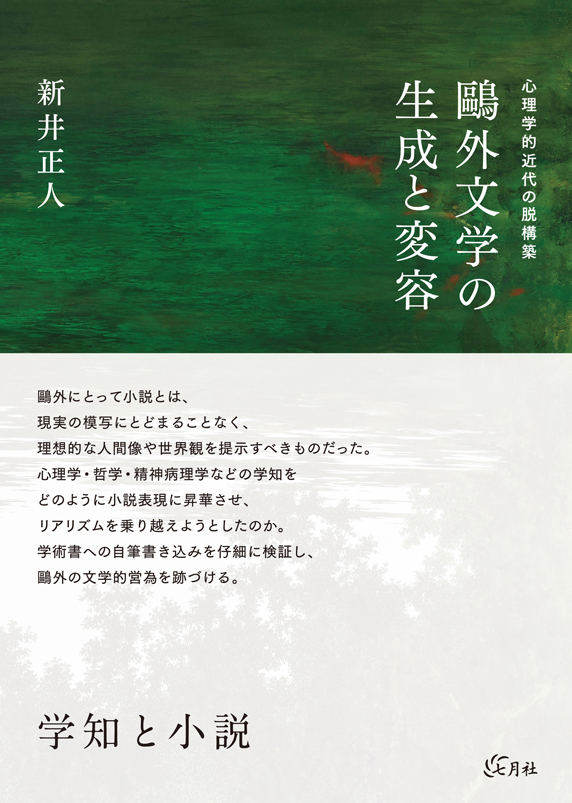
鷗外文学の生成と変容 心理学的近代の脱構築
定価:本体5,400円+税
学知と小説
森鷗外にとって小説とは、現実の模写にとどまることなく、理想的な人間像や世界観を提示すべきものだった。
当時最新の心理学・哲学・精神病理学などの学知を受容していた鷗外は、それをどのように小説表現に昇華させ、リアリズムを乗り越えようとしたのか。
学術書への自筆書き込みを仔細に検証し、鷗外の文学的営為を跡づける。
目次
序章 「小説を作るべき方便」としての「心理的観察」→公開中
Ⅰ 心理的リアリズムとしての近代文学
Ⅱ 近代心理学と近代文学の等質性
Ⅲ 初期鷗外の文学観
Ⅳ 鷗外文学の多形性
第一章 小説表現の学的構築 ─鷗外と心理主義─
Ⅰ 心理主義的時代思潮の影響
Ⅱ 帰納的形而上学への夢
Ⅲ 科学的心理学の受容
Ⅳ 人間心理の言語的構築
第二章 Seeleをめぐる論理 ─心身問題と鷗外─
Ⅰ 性質二元論の受容
Ⅱ 「主物」と「主心」の「併行」
Ⅲ 科学的心理学と心身問題
Ⅳ 「魂と肉体」の文学
第三章 構成的外部への理路 ─鷗外と識閾下─
Ⅰ 芸術創作理論と識閾下
Ⅱ 識閾下をめぐる学知
Ⅲ 表現戦略としての識閾下
Ⅳ 主体の構成的外部
第四章 「混沌」のもつ力 ─鷗外と教育思想─
Ⅰ 利他的行為の存立要件
Ⅱ 「選択の自由」としての自由意志
Ⅲ ヘルバルト教育学の受容
Ⅳ 「混沌」としての主体
Ⅴ 「将来ノ教育」の模索
第五章 “Vita sexualis”という言説装置 ─鷗外におけるクラフト=エビング受容─
Ⅰ 『性的精神病質』の日本への移入と鷗外
Ⅱ クラフト=エビング受容の様相
Ⅲ 「ヰタ・セクスアリス」の生成
Ⅳ 「告白」の不可能性
第六章 表象心理学と物語行為 ─鷗外文学の構築方略─
Ⅰ 表象心理学の枠組み
Ⅱ 心理の因果的構成
Ⅲ 「雁と云ふ物語」と心理描写
Ⅳ 「雁」の表現戦略
Ⅴ 「物語のモラル」、そして史伝へ
Ⅵ 近代の脱構築─おわりに─
初出一覧
あとがき
資料① G・A・リントナー『経験的心理学教本』受容の様相
資料② O・キュルペ『哲学入門』・『心理学概論』受容の様相
索引→公開中
人名索引
著作名索引
事項索引
著者
新井正人(あらい・まさと)
1986年、埼玉県生まれ。
2005年、埼玉県立川越高等学校卒業。
2009年、慶應義塾大学文学部卒業。
2017年、慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学。
博士(文学)。
現在、早稲田中学校・高等学校国語科教諭。
専門は、日本近代文学・国語教育。
主な論文に、「「肖像画家」に託された戦略─三島由紀夫「貴顕」における「芸術対人生」の問題系─」(『昭和文学研究』67集、2013年9月)などがある。