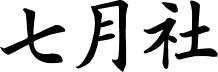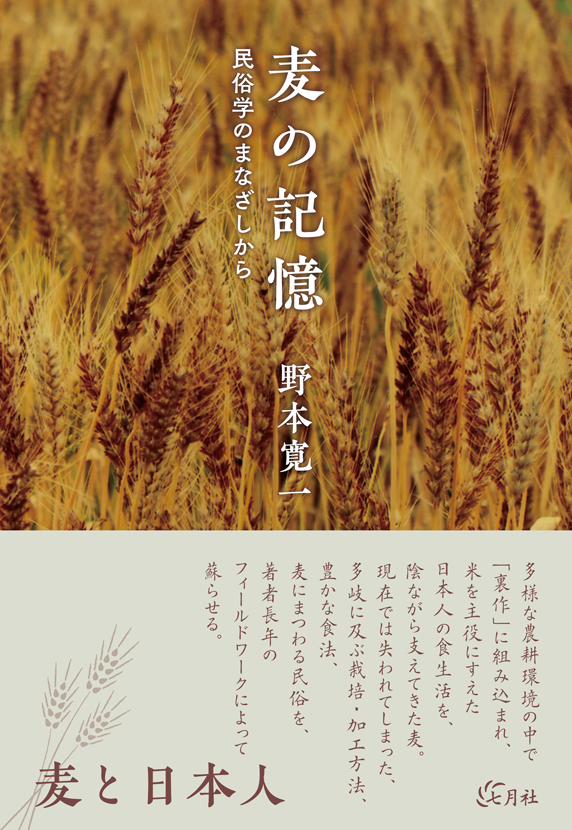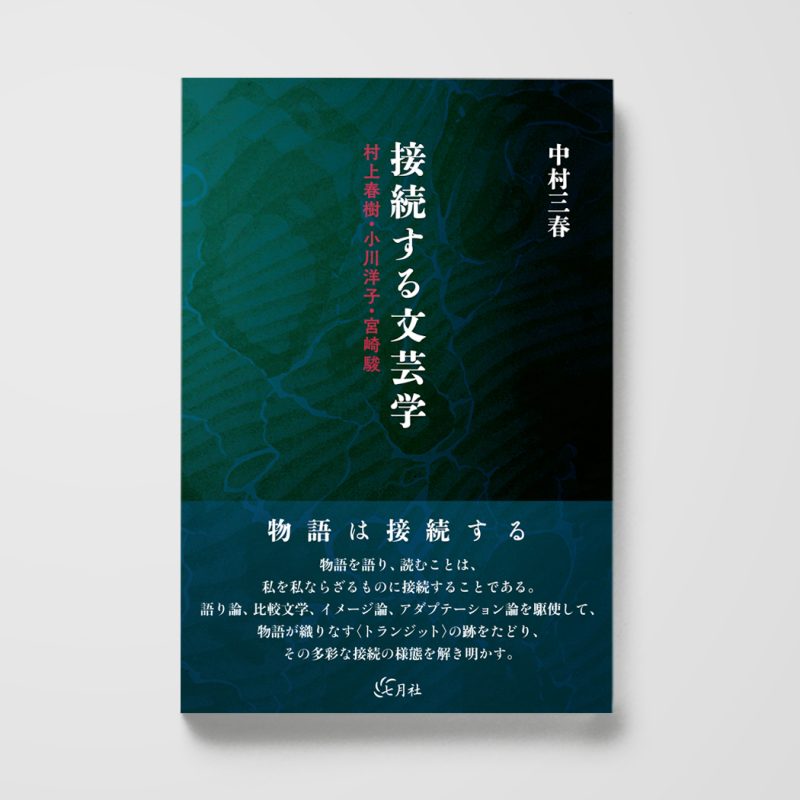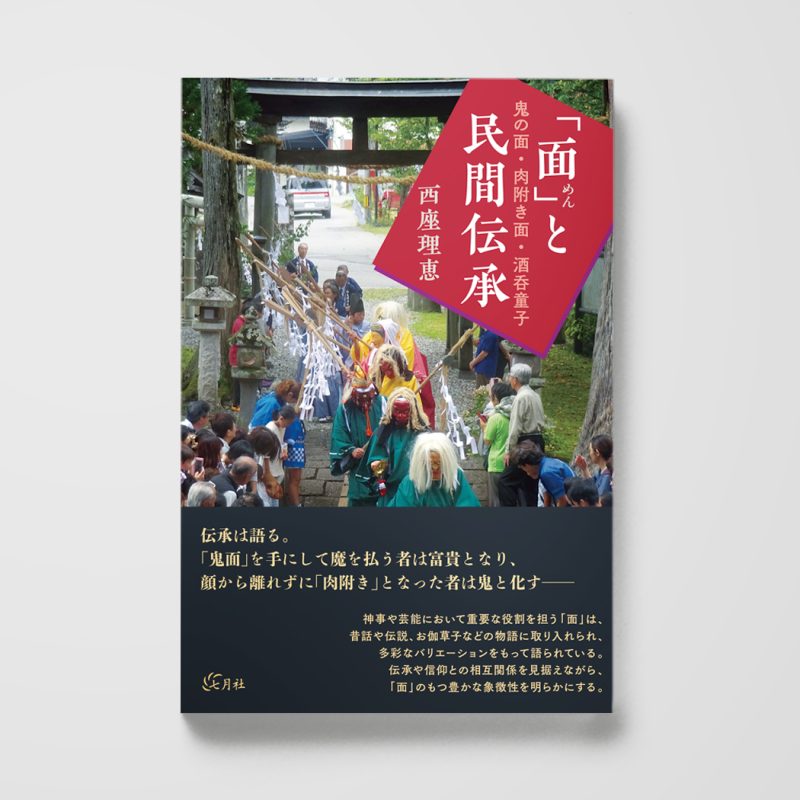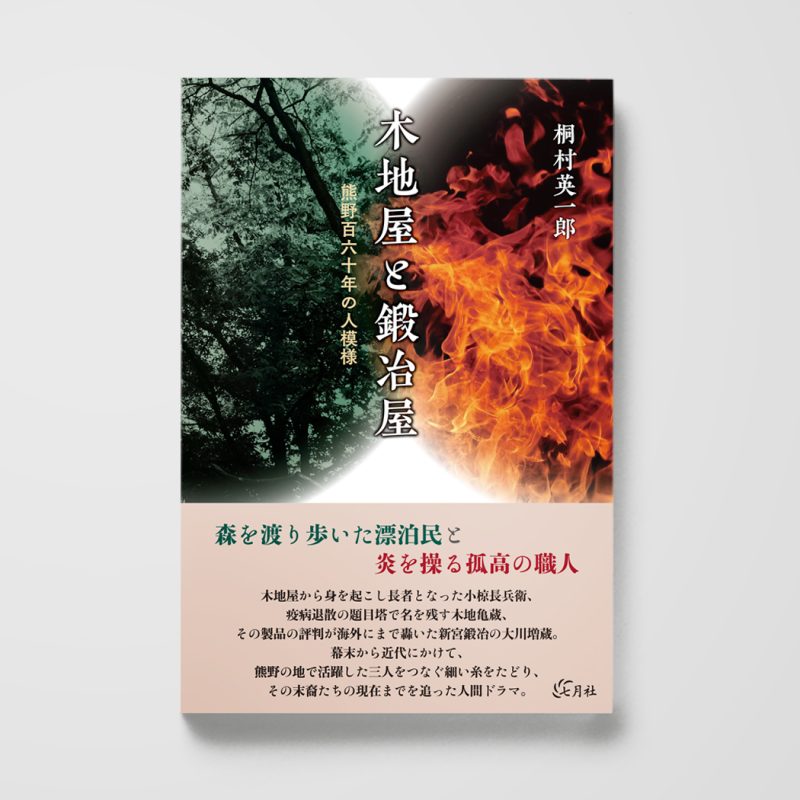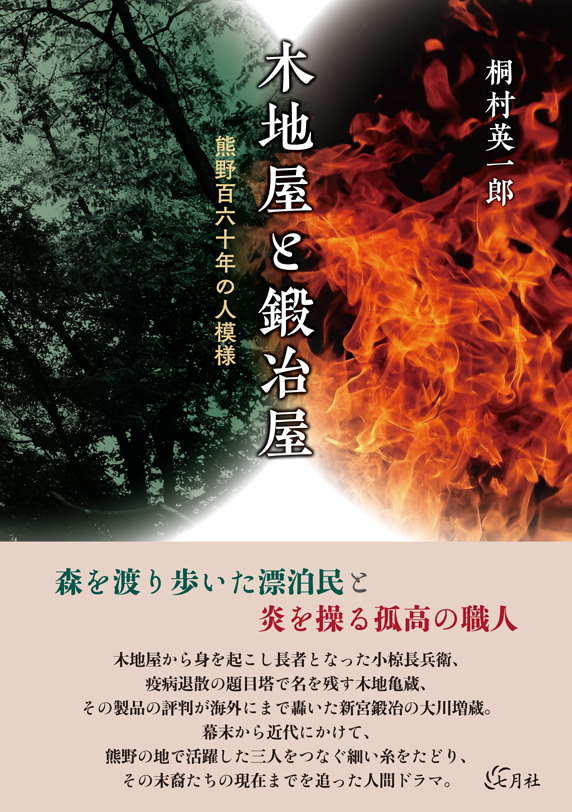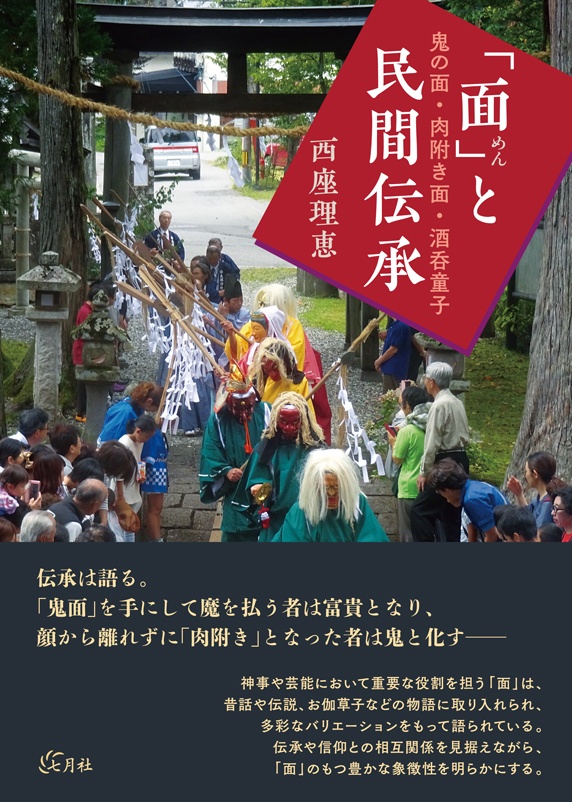麦の記憶
民俗学のまなざしから
定価:本体3,000円+税
麦と日本人
多様な農耕環境の中で「裏作」に組み込まれ、米を主役とする日本人の食生活を陰ながら支えてきた麦。
現在では失われた多岐に及ぶ栽培・加工方法、豊かな食法、麦の民俗を、著者長年のフィールドワークによって蘇らせる。
目次
序章 麦に寄せて
Ⅰ 麦の栽培環境
一 海岸砂地畑
二 斜面畑と段々畑
三 畑地二毛作と地力保全
四 焼畑と麦
五 牧畑と麦
六 水田二毛作の苦渋─田代・麦代の循環─
七 水田の湿潤度と裏作作物
八 麦と雪
九 沖縄の麦作
十 麦作技術伝承拾遺
Ⅱ 麦コナシから精白まで
一 麦焼きから精白まで─奈良県天川村栃尾の実践から─
二 穂落としの技術
三 脱粒
四 麦の精白
Ⅲ 麦の食法
一 大麦・裸麦の食法
二 小麦の食法
Ⅳ 麦の豊穣予祝と実入りの祈願
終章 麦・拾穂抄
あとがき
著者
野本寛一(のもと・かんいち)
1937年 静岡県に生まれる
1959年 國學院大學文学部卒業
1988年 文学博士(筑波大学)
2015年 文化功労者
2017年 瑞宝重光章
専攻──日本民俗学
現在──近畿大学名誉教授
著書──
『焼畑民俗文化論』『稲作民俗文化論』『四万十川民俗誌──人と自然と』(以上、雄山閣)、『生態民俗学序説』『海岸環境民俗論』『軒端の民俗学』『庶民列伝──民俗の心をもとめて』(以上、白水社)、『熊野山海民俗考』(人文書院)、『山地母源論1・日向山峡のムラから』『山地母源論2・マスの溯上を追って』『「個人誌」と民俗学』『牛馬民俗誌』『民俗誌・海山の間』(以上、「野本寛一著作集Ⅰ~Ⅴ」、岩田書院)、『栃と餅──食の民俗構造を探る』『地霊の復権──自然と結ぶ民俗をさぐる』(以上、岩波書店)、『自然と共に生きる作法──水窪からの発信』(静岡新聞社)、『生きもの民俗誌』『採集民俗論』(以上、昭和堂)、『自然災害と民俗』(森話社)、『季節の民俗誌』(玉川大学出版部)、『近代の記憶──民俗の変容と消滅』『井上靖の原郷──伏流する民俗世界』(以上、七月社)、『自然暦と環境口誦の世界』(大河書房)、『民俗誌・女の一生──母性の力』(文春新書)、『神と自然の景観論──信仰環境を読む』『生態と民俗──人と動植物の相渉譜』『言霊の民俗誌』(以上、講談社学術文庫)ほか
書評・紹介
- 2022-07-30「日経新聞」
評者:神崎宣武(民俗学者) - 2022-09-25「読売新聞」
評者:梅内美華子(歌人) - 2022-10-15「図書新聞」
評者:川島秀一(日本民俗学会会長) - 2023-winter「季刊 農業と経済」
評者:落合雪野(龍谷大学農学部)